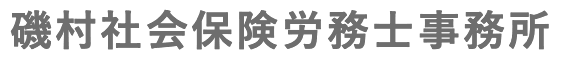労働時間は原則、1日8時間、1週40時間と定められています(労働基準法第32条)が、その例外として、「変形労働時間制」が設けられています。
一月や一年といった単位で業務の繁閑がある等の理由から、変形労働時間制を採用する企業は多いかと思われます。
そこで1か月単位の変形労働時間制を巡り、複数のシフトパターンにより労働させているケースにおいて、就業規則にすべてのシフトパターンが記載されていなかったとして変形労働時間制が無効とされた裁判例が出ています。
そこで今回は、変形労働時間制を導入・運用する際の注意点をとり上げます。
導入時の注意点

そもそも変形労働時間制とはどのような制度かと言いますと、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。
変形労働時間制としては、1ヶ月単位、1年単位などの仕組みがありますが、問題となった1ヶ月単位の変形労働時間制を導入にあたって、就業規則を整備する場合、以下のすべての事項を定めなければならないことになっています。
変形労働時間制としては、1ヶ月単位、1年単位などの仕組みがありますが、問題となった1ヶ月単位の変形労働時間制を導入にあたって、就業規則を整備する場合、以下のすべての事項を定めなければならないことになっています。
対象労働者の範囲
対象労働者の範囲に制限はありません。
全従業員にしても良いですし、一部の部署だけにしても良いのですが、その範囲を明確にしておかなければいけません。
全従業員にしても良いですし、一部の部署だけにしても良いのですが、その範囲を明確にしておかなければいけません。
対象期間・起算日
例えば「毎月1日を起算日とし、1ヶ月を平均して1週間当たり40時間以内とする」というように、具体的に対象期間と起算日を定める必要があります。
なお、対象期間は1ヶ月以内の期間であれば、2週間や4週間とすることも可能です。
なお、対象期間は1ヶ月以内の期間であれば、2週間や4週間とすることも可能です。
労働日・労働日ごとの労働時間
シフト表や会社カレンダーなどで、対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。
その際、シフト制労働者で月ごとにシフトを作成する場合には、全ての始業・終業時刻のパターンとその組み合わせの考え方、シフト表の作成手続き・その周知方法等を定めておく必要があります。
その際、シフト制労働者で月ごとにシフトを作成する場合には、全ての始業・終業時刻のパターンとその組み合わせの考え方、シフト表の作成手続き・その周知方法等を定めておく必要があります。
労使協定の有効期間
その他の点として、労使協定を定める場合は、労使協定そのものの有効期間は対象期間より⻑い期間とする必要がありますが、1か⽉単位の変形労働時間制を適切に運⽤するためには、3年以内程度とすることが望ましいです。
運用する際の注意点

複数のシフトパターンがある場合、就業規則には、代表的なものだけを記載しているようなケースや、様々なパターンに関する記載があるものの実態とずれているようなケースが見られます。
変形労働時間制が無効になった裁判例では、「原則として」と記載し、4つのシフトパターンを定めたのみで、すべてのシフトパターンを記載していなかったとして、労働基準法第32条2の「特定された週」または「特定された日」の要件を充足するものではないことから、変形労働時間制は無効であると裁判所が判断しました。
さらにはこの1か月単位の変形労働時間制における残業代(割増賃金)の計算については、複雑であり、運用に慣れるまでには時間もかかるように思われます。
変形労働時間制が無効になった裁判例では、「原則として」と記載し、4つのシフトパターンを定めたのみで、すべてのシフトパターンを記載していなかったとして、労働基準法第32条2の「特定された週」または「特定された日」の要件を充足するものではないことから、変形労働時間制は無効であると裁判所が判断しました。
さらにはこの1か月単位の変形労働時間制における残業代(割増賃金)の計算については、複雑であり、運用に慣れるまでには時間もかかるように思われます。
最後に

ひとつの裁判例ではありますが、会社は、就業規則にすべてのシフトパターンの記載があるかを確認し、記載がなければ追加しなければなりません。
また、今後において、記載されたシフトパターン以外の時間で勤務しないように管理していくことが求められます。
現状、導入していても中々上手く行っていないケースもある様で、事業主の方に限らず、担当の従業員の方でも、一度身近な社労士にでもご相談してみてください。
きっとお役に立てるものと思います。
また、今後において、記載されたシフトパターン以外の時間で勤務しないように管理していくことが求められます。
現状、導入していても中々上手く行っていないケースもある様で、事業主の方に限らず、担当の従業員の方でも、一度身近な社労士にでもご相談してみてください。
きっとお役に立てるものと思います。